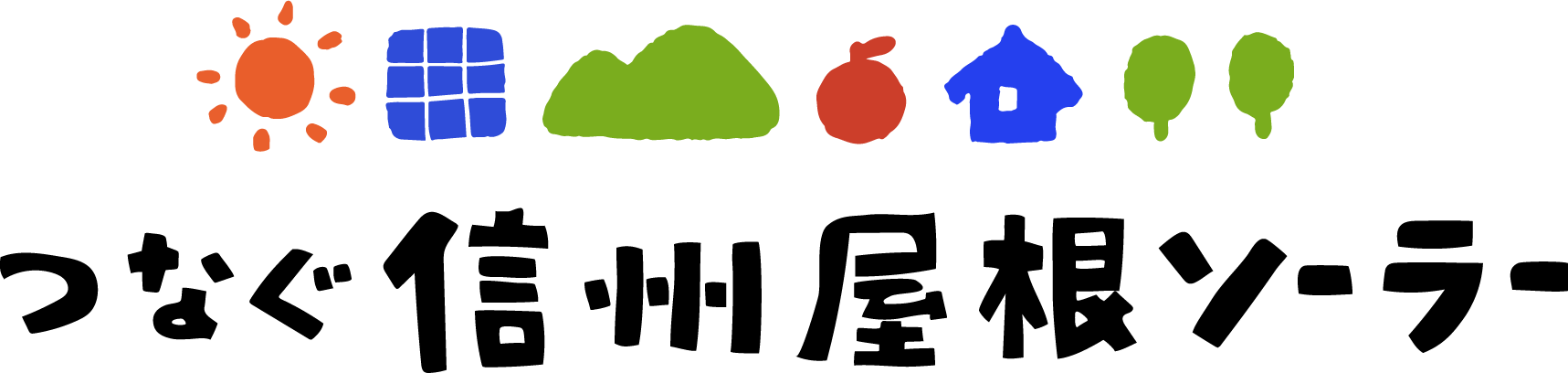SOLAR ECOLOGICAL
SHINSHU太陽光発電が、
信州の未来をつなぐ。
ETHICAL
LIFE FOR EARTH
クロストーク
SAMNICON:宇南山 加子さん
長野県環境部環境政策課ゼロカーボン推進室 再生可能エネルギー係:小西 優衣さん
moves.クリエイティブディレクター:渡邉 オヴさん
クロストーク
SAMNICON:宇南山 加子さん
長野県環境部環境政策課ゼロカーボン推進室 再生可能エネルギー係:小西 優衣さん
moves.クリエイティブディレクター:渡邉 オヴさん

宇南山さんが入手した土地は、御代田町の「普賢山落」と呼ばれる集落。1960年代から東京の第一線で活躍するクリエイターたちが移り住み、コミュニティを形成したところ。
長野県御代田町の「普賢山落」と呼ばれる集落は、1960年代から東京の第一線で活躍するクリエイターたちが移り住み、コミュニティを形成したところ。この土地に、東京の下町から移り住んできたのが、宇南山加子さんとパートナーの松岡智之さん。プロダクトデザインを生業とする二人がこの土地の歴史を知ったのは土地の購入後。だからなおさら、導かれてここへ来たように感じるという。
二人は、高く茂ったカラマツ林を伐り拓き、自分たちで設計した家を建て、庭に水路と池を掘った。そこには太陽の光が注ぎ、風が吹き、水が流れ、土が緑を育んでいる。再生可能エネルギーを無理なく循環させる仕組みを、自分たちの手でつくり出している。
今、長野県ではゼロカーボン社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの利用を推進し、なかでも太陽光を利用した屋根ソーラーの普及に力を入れている。
自分の家で使う電気は、自分の家で創り出す—それが当たり前の社会の実現は、難しいことではない。そこに屋根があるのなら、太陽光パネルをのせればいいのだから。
本当の豊かさとは、そこにある恵みに気づき、生かすことだと宇南山さんは言う。太陽の光は等しく注ぐようでいて、長野県はことに日差しが強い。その恵みを享受しない手はない。



左上_宇南山加子(うなやま・ますこ)さん。日用品のプロダクトデザイン、店舗などのディレクションをするデザイン会社「SyuRo」の代表取締役、デザイナー。台東区に店舗を構えつつ、2023 年に長野県御代田町に移住し、ギャラリー「SAMNICON」をオープンした。
右上中_小西優衣さん。長野県環境部ゼロカーボン推進室で再生可能エネルギー係として勤める。
右上下_向かって右は信州移住マガジン『moves.』のクリエイティブディレクターであり、福島県から東御市への移住者でもある渡邉オヴさん。
電気代を払うために 子どもを預けて働いているのか……と
—— 震災やコロナ禍を機に移住を考えたり、エネルギー問題と向き合うようになった方は多いと思いますが、お二人はいかがですか。
渡邉オヴさん(以下、渡邉) 僕は福島県の郡山市に住んでいましたが、2011年3月の東日本大震災があって、福島第一原発の事故も起きました。当時、長男が保育園児で、下の子が2月に生まれたばかり。放射性セシウムが拡散されたのを不安に感じて、妻と子どもは知人を頼って東御市へ避難し、その後、家族そろっての移住を決めました。
家を手に入れて、母屋とガレージの屋根に目一杯、太陽光パネルを設置しました。お金はかかりましたが、発電して売電ができるし、そもそも自分たちでエネルギーを生み出すことが一番の目的でした。
宇南山加子さん(以下、宇南山) 私は東京蔵前の下町育ちで、下町ならではの人づきあいや行事が楽しくて、子育ては下町でしたいと思っていました。その一方で、週末は釣りをしたり、山に登ったり、子どもを連れてアウトドアを楽しんでいました。友人が2011年の震災を機に北海道へ移住して、毎年のように遊びに行くようになったんですが、ある時、知床のとあるお宅を訪ねる機会がありました。家の真ん中に小さな焼却炉があって、その上にコンロがついて煮炊きできるようになっているんです。家の中にめぐらせた道管を通し、焼却炉の熱で温めたお湯をバスルームの上にためる仕組みです。
ごみを燃やして部屋をあたため、三食のごはんをつくって食べ、お風呂にも入れる。エネルギーを無駄なく使って、みんなが幸せになれる家に、ものすごい衝撃を受けました。

宇南山さんが手にするのは、自身が手がけ、日本とデンマークのデザインを取り入れたインテリアブランド〈MOTARASU〉の「ユニオントレイ」。
当時シングルマザーの私は、ワンオペで子育てと仕事をしていたのですが、働くには子どもを保育園に預けないといけない。ではなぜ働くかというと、やりがいと生活費に加えて、電気代や家賃を支払わないといけないからなんですよね。本当は子育てをしたいのに、私は電気代を稼ぐために子どもを預けて働いているのかなって、すごく矛盾を感じましたし、なんてエネルギーを無駄づかいしているんだろうと、疑問視するようになったんです。
それからエネルギーのことを勉強して、パーマカルチャー※1のことを知り、子どもが独立したら、どこか郊外に移ろうと決めました。この先、災害や食糧危機などが起こった際に、子どものために必要なのは、土や水があるところに居場所をつくることだと思ったんです。
—— 御代田町を選んだのは、なぜですか。
宇南山 移住先には五つの条件がありました。釣りやアウトドアが好きなので、川や海があり、標高1000mくらいの森のような場所で、東京からも近い。そんな場所を、あちこちめぐりながら探していたんです。
ある時、仕事で御代田を訪れ、空気がカラッとして、風が吹いて、気持ちのいいところだなと感じました。海がないことから長野県は候補に入れていませんでしたが、海さえ我慢すればいい場所でした。後に、日本海まで1時間半だと聞いて、条件がそろったなと。
※1:パーマカルチャー パーマネント(永続性)、アグリカルチャー(農業)、カルチャー(文化)を合わせた造語で、持続可能な暮らしをデザインする考え方。


左上_住居1階は、庭に面したLDKがひと続きの空間。窓の外にはウッドテラスがある。テーブルや椅子、ソファは松岡さんのデザイン。
右下_グレーの壁は、石の左官材で仕上げた。玄関から入って部屋の一番奥(写真では手前)をカーテンで仕切れば、寝室になる。
—— ご自宅は宇南山さんご自身で設計されたのでしょうか。
宇南山 パートナーの松岡と一緒に設計プランを立てました。朝日で目を覚まして、朝風呂に入って……。それから台所に立つと天窓から光が射し、午後にはギャラリーに日が入ります。昼間は電気を使わず、自然光だけで十分に明かりが採れるように設計しました。自分たちで使う電気は自家発電するため、夏と冬の太陽光の角度も考えて屋根の角度を決めて、太陽光パネルを設置しました。
木造ですが、外は石の断熱材を施して、中は石の左官材で仕上げて、石の家のような造りです。しっかり断熱してあるので、PS※2で0.3kWしか使わずに、1年を通して21℃を保つことができます。
—— 外は残暑が厳しいですが、暑さを感じませんね。
渡邉 長袖でも半袖でも、暑くも寒くもない。とても過ごしやすいです。
宇南山 自然の風が心地いいので、扇風機もクーラーもいらないんですよ。庭には水路と池を掘り、生活排水を流してためます。微生物や植物の力で浄化するバイオ・ジオ・フィルターの仕組みです。池からオーバーフローした水は畑に流して野菜を育て、ポンプアップした水は再度水路に戻して循環させています。
※2:PS パネル式放射冷暖房システム。ラジエーター内に夏は冷水、冬は温水を循環させ、断熱の効いた室内を一定の温度に保つ。



左上_建物に向かって左側がギャラリー。伐採したカラマツを乾かして製材し、外壁材に用いた。
右上中_住居とギャラリーをつなぐ半屋外のスペース。ポーチであり、仕事場でもあり、第二のリビングのような居心地のいい空間。
右下下_宇南山さんいわく「デンマークのデザインは、じつは日本の影響を受けている」。だからこそ通じるものがあるという。
あと、ここはもともとカラマツ林だったんですが樹齢が高く、かなり伸びていて、周囲に影を落としていました。倒木が心配だからと、まわりの家に頼まれて、100本ほどあったカラマツを泣く泣く伐ることにしましたが、伐採した木は無駄にせず、建材として使いました。
太陽光、風、水、土といった再生可能エネルギーをいかに取り入れ、自分たちの体を通して循環させるかを考えました。自給自足を目指すというより、自分たちが心地良く過ごせることに重点を置いて設計しました。
渡邉 どこを切り取っても美しく、心地いい家と庭ですが、じつは合理的な考えに基づいている。宇南山さんや松岡さんの手がけるインテリアデザインと同じですね。
宇南山 ありがとうございます。私がデンマークのブランドのデザインもしていて、松岡が留学していたこともあって、デンマークに行く頻度が多いんですが、デンマークは環境大国と呼ばれていて、日本との住宅性能の違いを感じます。それでも長野県にはトリプルガラスのサッシをつくるメーカーがあったり、国内では先進的だと思います。
渡邉 屋根ソーラーについては、僕はそこまで深く考えたわけではなく、屋根があるなら付ける、の一択だったんですが、長野県でもまだあまり普及していないんですよね。
小西優衣さん(以下、小西) そうですね。長野県内にある住宅の屋根のうち、太陽光パネルがのっているのはまだ1割台です。
—— 屋根ソーラーがなかなか普及しないのは、売電価格が下がっているからでしょうか。
小西 確かに、固定価格買取制度※3の開始当初から比べると、買い取り価格は大きく下がっています。ただ、これは設備費用の低下に合わせているからで、電気代の節約や売電で初期投資を回収できる年数は13年くらいのまま、じつはほぼ変わっていません。
太陽光で発電する電気のうち、家で使う割合を自家消費率といいますが、だいたい3割前後といわれます。これを高くするほどお得になります。今は電気代が高いので、普通に使っていれば、屋根ソーラーを導入して損することはないと思います。
宇南山 うちの太陽光パネルは10年リースなので、初期投資は0円。毎月1万3〜4千円払うのと、蓄電池はつけていないので夜に使う分は買いますが、昼間は使う分を上回る発電ができるので、余った分は売電して実質、電気代0円です。
ただ、リース対象の太陽光パネルのデザインが好みでなかったので、事業者に頼んでアメリカのマキシオンを組み込んでもらいました。耐用年数40年で、発電効率がいいから枚数が少なくて済む。同じ屋根の広さなら、たくさんつけるほど発電量は増えますよね。
私たちは自分で調べて選びましたが、こういった選択肢があることが、もっと広く知られるといいなと思います。
※3:固定価格買取制度 再生可能エネルギーで発電した電気を国が定める価格で一定期間、電力会社が買い取ることを義務付ける制度。FIT制度ともいう。



なんでもつくる宇南山さんたちは水路も池も自分たちで手がけた。キッチンやお風呂、洗面で使った排水はバイオ・ジオ・フィルターを通って池にたまる。
太陽の恵みがリンゴになるか電気になるか。
どちらも地域の特産品のようなもの
—— 県でも屋根ソーラー普及のための取り組みをされていますね。
小西 はい。長野県内の屋根ソーラーの情報をまとめた「つなぐ信州屋根ソーラー」という県のポータルサイトができましたので、ぜひ多くの方に見ていただきたいです。
じつは長野県は太陽光発電に向いているんです。標高や澄んだ空気のおかげか、日射強度という地表に到達する太陽光の強度が高い。それから太陽光パネルは熱くなると発電力が落ちてしまうんですが、長野
県は比較的気温が低いので効率がいい。そういうこともあって、長野県では太陽光発電を再生可能エネルギーの主力として推進しています。
宇南山 カラマツを伐ったのも、無駄ではありませんでした(笑)。
—— メガソーラーをつくることに比べれば、環境負荷は小さいですね。
宇南山 そうですね。森を残すことも大事ですが、手を入れることでまわりの家の人たちも明るくなったと喜んでくださったし、私たちも太陽の力を最大限に活用できるようになりました。
伐ったあとには好きな木を植えて、自分たちなりの森を育てているところです。ヘーゼルナッツの木も植えました。長野市の「ふるフル」という生アイスのお店から苗木を購入し育てるんですが、実を収穫して余ったら、買い取ってもらえるんですよ。

ギャラリー「SAMNICON」には、松岡さんがデザインした家具が置かれ、宇南山さんがデザインあるいはセレクトした日用品が並ぶ。
—— 自分たちが食べて終わりではない仕組みなのですね。
小西 宇南山さんの取り入れている循環する仕組みや、自給自足だけが目的ではないという考え方は、県も一緒です。また県の施策でゼロカーボンを目指すことは前提にありますが、まずは快適であることが大事です。
渡邉 温暖化対策は必要ですが、それだけが目的では、なかなか広まらないですよね。
小西 そうなんです。使うエネルギーをなるべく減らして、使う電気は再エネで、それが気持ちいいというのがコンセプトです。
自分で使うものを自分でつくれるのは、気持ちがいいことだと思うんですが、宇南山さんはいかがですか。
宇南山 やっぱり気持ちいいですよ。たとえば、電気代がかからない分、おいしいものが食べられるし、小さなお子さんなら習い事をさせられる。もっと豊かなこと、もっと人が喜ぶことに投資ができます。
小西 県も、地域でつくったものを自分たちで使い、さらに循環させていくことが大事だと考えています。これからも、住み心地のよい長野県が続いていくように、みんなの暮らしが良くなっていくように。
電気も地域の特産品のようなもので、いろんなエネルギーを生み出すポテンシャルが長野県にはあるんです。
宇南山 太陽は等しくそこにあって、それがリンゴになるのか、電気になるのか。あとは、リンゴや電気が買うものだという固定観念を取り払わないといけない。
渡邉 なるほど。自分でつくるという選択肢もありますね。
小西 電気も自分でつくることもできますし、つくった電気は使うことも売ることもできます。自分で使う分だけつくってもいいし、たくさんつくって売ってもいい。それぞれの考え方で選べるのが、屋根ソーラーのいいところだと思います。
宇南山 そこにあるものの恵みに気づくことが大切で、あるものを有効活用すれば、多くを望まなくても、みんなもっと豊かに暮らせます。それがゼロカーボンで到達するべきことだと思います。
渡邉 屋根があるなら太陽光パネルをのせる。それが特別なことではなく、誰にとっても当たり前のことになればいいですね。なんのリスクもないことは、僕自身が実感しているところです。
宇南山 県や国や企業が率先していってほしいですし、私たちの「SAMNICON」というギャラリーも、暮らし方を提案する場にしたいなと思っています。みなさんにエネルギーの話をすると、共感をもって自分にもできるかもしれないと思ってくださるんですよ。これからも、いろんな選択肢、いろんな生き方があることを示してきたいと思います。
—— ありがとうございました。


左上_年間の太陽光の角度を計算し、屋根の向きや角度を決めて、建物を設計した。太陽光パネルのリース期間が終わったら、蓄電池を取りつける予定。「蓄電池も、その頃にはきっと性能は上がって価格は下がっているはずです」。
右下_カラマツを伐採したあとに、ブナ、アオダモ、カツラなどの広葉樹を植えた。数十年後には針葉樹林あらため心地良い雑木の森になるだろう。
記事本文、写真等は信州移住マガジン「 moves.(ムーヴス)」Vol.03及び、「住まいnet信州」Vol.44より転載しています。
・moves.サイト https://moves-life.jp
・住まいnet信州サイト https://www.sumainet-shinshu.jp